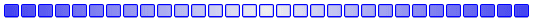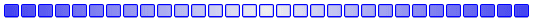『戦闘メカ・ザブングル記録全集 4』 発行/日本サンライズ(1983年7月) P184-185
メカ・ロン
富野由悠季
※太字・・・実際には傍点
※〈 〉・・・実際にはルビ
●総論
メカ・ロンをきちんと書くと “メカ論”。
こんなことで一文をものにしようというほどの ことではない、と常々考えている。
だから、この種の原稿は書かないように心掛けていた。
しかし、ザブングルという仕事は、いろいろな問題が明確にあらわれているので、それについてのメモを残しておく。
●玩具〈がんぐ〉ザブングル
玩具、おもちゃの意味であり、おもちゃの項目を小学館の国語大辞典で調べるとこうある。
〔翫物〕
(1) 子供の遊び道具。
(2) なぐさみのためにもてあそばれる人や物。
(3) 本格的でないものや、安っぽいもの。
どうだろうか? ひどく含蓄のある言葉、意味だといえないだろうか?
殊に、僕の場合、急遽、総監督をやれと言われたために、僕が企画の洗い直しをした時には、ザブングルのキャラクターは決定されていたために、このキャラクターには本当に困ったというしかなかった。
確かに、ガンダムもイデオンも玩具発想ではあったのだが、キャラクターの決定までの経緯は知っていたし、それに抵抗したり、覚悟を決めていったりして作品創りに入っていった。
しかし、それでも無理な合体コンセプトを持ったイデオンを合体、分離させて活躍させなければならない事には、最後まで悩みぬいた。
だから、イデオンの発動篇に至っては、合体コンセプトを一切すてて、巨人として扱うことによって、玩具からの脱却を図ったわけである。
その仕事と同時に、ザブングルを見せられた時は、本当に正直、いいかげんにして欲しいと思った。
なぜ、玩具だけが正攻法的な商品として認められるのか、という企画者の発想のナレアイさ加減にうんざりさせられた。
はっきり言って、ザブングルは原案者とデザイナーの玩具的発想から脱出できないところに問題がある、と言いきれるのである。
●デザイナーの習性
ならば、ザブングルのメカニック・デザイナーの大河原氏に全ての責任があるのか、というと、これが違う、といい切れるから、不幸なのだ。
責任が一人の人間〈スタッフ〉に起因すると言いきれる事態は、明瞭に改善策を打ち出せるから問題は深刻でない。
むしろ、大河原氏を起用して、クローバーというメーカーのコンセプトに合わせたメカニックを想出しようとした、日本サンライズの矢立以下のスタッフの発想に問題がある。
が、クローバーは玩具メーカーであるから玩具を作れと命令することに道義的にも物理的にも間違いは一切ない。
玩具で商売をして生きてゆかねばならないクローバーは、売れる玩具の企画を注文するために日本サンライズとコンタクトをとったので、この原因をもって、スタッフなり視聴者が疑義をとなえることは間違いなのだ。
問題は、受注者の日本サンライズの部分の安易な玩具発想に全ての原因があるといって良いだろう。
大河原氏は、日本サンライズの仕事を受注し、日本サンライズの基本コンセプトを受け入れつつメカニック・デザインをする立場であるから、全て、やむを得ない結果なのである、といえる。
しかし、メカニック・デザイナーの習性として、この受注仕事をしてやってゆくうちに、いつしか、この玩具的発想にとらわれてしまって、この習性から脱け出られなくなってしまうという問題がある。
これは、大河原氏個人の問題として、彼が現在一番苦慮している事である。
が、一度、手が憶えてしまったことを忘れさせることはなかなか出来ない。
これは、ザブングルのゲスト・メカのデザインをやって貰った出渕君にも言える。
彼の場合、大河原氏よりは二世代若いデザイナーで今後、まだまだ変り得る素養を持っているにもかかわらず、現時点でいえば、一度、憶えたテクニックというものにこだわってしまって、なかなか脱皮できないという傾向がみられる。
これは、出渕君がガンコな人だから、ではない。
大河原氏と同じく、デザイナーは肉体労働者なのだ。一度、手が、体が、憶えてしまったものを、なんとかしようと意識しても、これを洗い流してゆくためには、莫大な精神力と訓練がいるのである。
つまり、初心者があるレベルまでゆく訓練を1とすると、一度憶えたものを洗い流して次のステップにゆくためには、七、八倍の努力を要求される。
まして はじめのレベルに自信を持ってしまうと、この洗い流し作業に入ろうとするだけで七、八年の時間はあっという間にすぎてしまい、結局は、時代にとり残されるということになる。
これがデザイナー(および、あらゆる肉体労動者)に課せられた宿命なのだと憶えてもらいたい。
そうでなければ、画だけで売り出したコミックス・ライターなりイラストレーターが十年もしないうちに若手に追い抜かれる、などということは、金輪際ないはずなのだ。
●ゲスト・メカたち
ザブングル以外のメカニックについては、僕のザブングルとアイアン・ギアーへの拒否反応から出た結果といえる。
そうはいっても、ダッカー(※原文ママ)などは前の企画の時代のものを使わざるを得ないスケジュールであったために、僕は、ギャロップ、トラッド・タイプにウォーカー・マシンの原型のイメージをとり入れようとかなり必死の思いで、出渕君に注文を出した憶えがあるのだが、出渕君はなんと言っているだろうか?
殊に、ギャロップの出来に関しては、W・Mの原イメージを投入出来たという嬉しさがあるものの、作品上の大欠点を生み出してしまった。
ザブングルの全長とギャロップの全長の違いが大きいために、W・Mのコンセプトをとるとザブングルが浮き上り、ザブングルをメインにするとギャロップがみえなくなるという問題である。(ジオラマが成立しないという事でもあるがね)
これは、作品という一つの世界をつくる上で、最も恥ずべき結果である。
本来、一つの作品世界で描かれるべきものが、あまりにも異ったイメージのもののゴッタ煮であってはならない。
これは、原則である。
それ故、僕にとって記録全集という存在は嫌悪すべき存在以外のなにものでもないのは、これらゴッタ煮の最たるものの羅列が為されるからである。
監督の不見識の展覧会といって良い。
●湖川メカニック・デザイナーの問題
で、この不見識、ゴッタ煮のメカの総覧を見てお分かりの通り、さらに不協和音を増大させているのに、湖川デザインの存在がある。
こうなると、一人の総監督が何をいおうと、好き勝手、いろんなメカのオンパレードで、一世界の運命協同体的なイメージなぞは総崩れということになる。
湖川氏はアニメーターである。アニメーターでおのれの手を慣らしてきた労働者であるわけで、これはこれで一度身についた技術をどうこうしようとしても、なかなか、である。
その湖川氏がメカ・デザインをやらせろと言い出すのは、僕の仕切りでやっているとリアルっぼい指向ばかりに面白さがなくなり、湖川氏がガマンできなくなるのである。
で、湖川氏の造型センスをベースにし、かつ、アニメー卜しやすいメカをなんとか開発してやうということになる。
ここには当然、出渕君の発想とも僕の発想とも根本的に異なる造型があらわれ、僕にしてみれば、自分でデザインのクリーン・アップができないから、結局、湖川メカを使わざるを得なくなる。
「もう少し、リアルっぼくならんのかね。W・Mとしてさ」
「こんなもんです。なんせ、バラエティ・ショーなんでしょ?」
と、湖川氏は、もともとザブングルのメカニックのコンセプトがないところを突いて自分のメカを作品に登場させようと圧力を加えてくる。
確かに、一人の監督なりデザイナーのセンスでは、どうしても、一〈ワン〉コンセプトで固りすぎてしまう。
湖川氏にしてみれば、その辺か面白くないというのが分かるから、僕も湖川メカを認めざるを得ない。
●ギャリアー以後
そして、サブ・キャラとしてのギャリアのデザインについて難儀していると、またも大河原氏の出現となり、彼は岡目八目の優利さで、「W・Mのコンセプトが番組を観てよく分かったから……」
というそれだけの理由で、出渕、湖川と僕もなーんもいえないギャリアのデザインをポンと持ってくるのである。
この大河原氏の突然の豹変も、彼の中で、デザインのあり方を変えたい、W・Mというのは何か、と考え続け、秘かに手を変える訓練をしていたからだ。
明らかに、ザブングルとは一線を画する仕上りとなっている。
このギャリアーの出現によって、ザブングルのメカニックの展開はより鮮明になったといえる。
演出者と画描きのレベルが一致した、とでもいおうか……。
ようやく、実体が現われ、ボリュームがついたW・Mの世界がみえてきた時に、僕はようやく、小型ランド・シップ “ウルフ” のコンセプトもより明瞭に作品に定着するだろうと信じたものである。
が、
W・Mの世界が、まずはザブングルとアイアン・ギアーで始ったという不幸さはやはり払拭しきれずに終った事は間違いない。
それは、玩具を売るべき世界に、らしさを投入した演出者のエゴがあったからだ、といいきれる。
しかし、描くべき世界に連動するメカニックというものはあり得るということを、ザブングルは教えてくれた。
その教訓をもって、もっときれいなメカの描写にチャレンジしてみたいものだ、と秘かに思う。
|